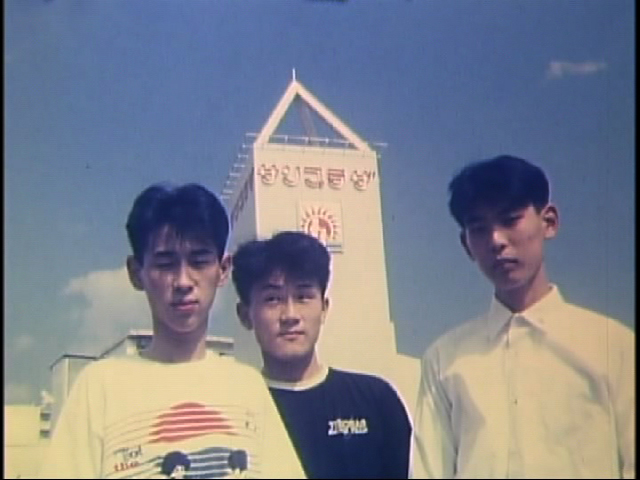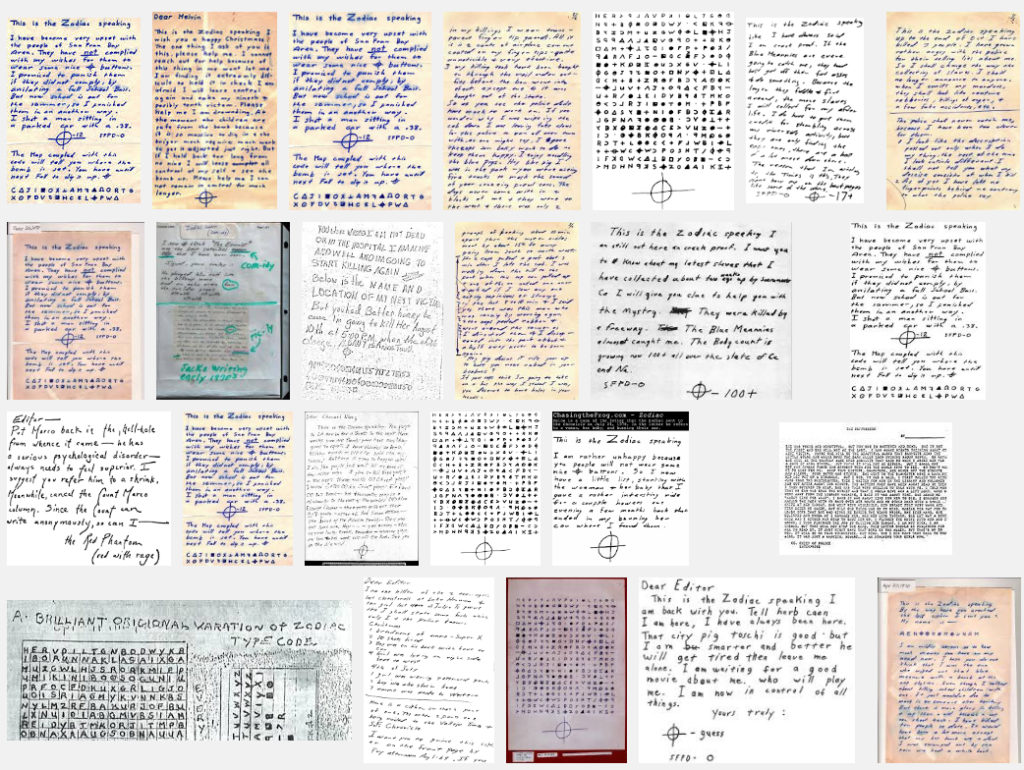event
宇多村英恵×木下令子オンライン対談(後半)
2021年12月28日

会場風景
ー宇多村さんは、国際芸術センター青森(ACAC)でのレジデンス後、ニューヨークに戻ってすぐにパンデミックが始まり、その後妊娠と出産を経験されていらっしゃいました。2019年まで制作のフィールドワークとして世界各地へ赴いていた宇多村さんが、それとは対照的とも言えるような内的な時間を過ごされていたというのは、すごく興味深いと思いました。同時にこの展覧会を含め国外の展覧会に参加の際には現場に立ち会えず、作品だけが海を渡って移動するという経験もいくつかされていますよね。さまざまな変化や新しい経験を経て、今はどのような実感を持って生活されているんでしょうか?
宇多村:身体というのは日々の小さな変化はあっても、そんなにドラマチックには変わらないものだと思っていました。今までは外界が宇宙のような感覚があり、主に外界と自分との間の関係を見つめていました。でも妊娠してからは内的な変化が大きく、最近は家というものは本当に小宇宙なんだと感じさせられます。例えばサハラ砂漠で撮影した映像作品※3の中で、掃除をしているような繰り返しの行為も、料理をして掃除をして、片付けるんだけど子供にまた散らかされて、という行為に似ている。無秩序の状態でモノがあると、子供も、何から手をつけていいかわからないようなんです。これはキュレーションの行為に近いと思うんですけど、箱などを使ってモノをある程度の秩序を持って配置してあげると、子供も探り甲斐がある様子です。子供にとってはそれがまさに仕事、生きる営みなんですね。そして、生まれた子供は気がついたらすごく大きくなっている。繰り返している行為はほぼ同じだけれど、その中に変化があるということの発見がかなり自分の中で変わったことです。変わらない中にある変化というのでしょうか。そういうものに敏感になりました。

※3 宇多村英恵「Wiping the Sahara Desert」2010 HD Video Performance
似たような体験としては、展覧会のためにドイツに送った作品が、その後別の展覧会でニューヨークを経由してから最近自宅に戻ってきました。物自体は変わっていないように見えても、展覧会や多くの鑑賞者のエネルギーを内包して前とは変わっているような気がしています。
今回のクラウトラウムの展覧会も、移動の制限で展覧会に立ち会えなかった切なさはあります。それを前提とした上で、出来事と経験にズレが生じた時にその中で生まれる想像の時間を、このコロナ禍が生んだ副産物として感じてみると、新しい見方もできるのではないかと思っています。デジタル社会では、出来事とコミュニケーションの時空の同期化が進んでいて、ズレの隙間時間が減り、時間に追われている感覚があったなと思うのですが、会えない時間だったり、待つという時間も、以前はなかった時間の過ごし方だなと。
ー離れているがゆえに14時間の時差の存在はすごく大きく感じていました。
木下:なんでもすぐに既読が付いて連絡手段のスピードが速くなり過ぎているからこそ、その速度にのまれずに距離や時差を想像していたいというのはあります。人が生きる中で実際ゆるやかに起こっているようなことを見つめていたい。展示の準備期間を含めて、私は宇多村さんの生活リズムをすごく意識して過ごし始めていました。生活に自然と待つ時間が生まれていて、生活を一呼吸して見直した瞬間がありました。
ー今回展覧会のメインビジュアルには大木裕之さんの映画作品からあるワンシーンを切り取って使わせていただきました。映画には、その映画の中に流れている時間というものがそれぞれにあって、このように切り取って静止画にすることで本来感じられていた時間性や文脈は当然削ぎ落とされてまったく別のものになる。事前の情報と、展覧会に足を運ぶという経験との差異をコロナ禍にあって自分自身もう一度確かめたかったという経緯もあってこの方法を取りましたが、実際会った人にチラシを渡すと「この写真SNSで見ました」と言われることが本当に多く、イメージが浸透してそのまま流れ去っていく速さに今更ながらというか、改めて驚いてしまいました。展覧会をあたかも代表するような1枚のイメージを決定することも、いつも難しいと感じています。
一方で、今回出展いただいたものではありませんが、宇多村さんのシークレットパフォーマンスシリーズの映像作品はフォトジェニックな要素が強い印象を持っています。映画やストーリーのある映像作品とは性質がまったく異なりますが、宇多村さんはご自身の映像作品をどのように捉えているんでしょうか。
宇多村:あの作品に関しては写真と映像の性質が両極で動いていると思っています。基本的にはシーンがカットされて切り替わってということはなく、ずっと同じ構成なのでとても写真的な映像です。写真で見ても動いているところを想像させるようなスチールだと思っています。正直なところ、ずっと見なくてもいい映像なんですよ。そこに佇まいとしてあると言ったらいいんでしょうか。だからあのシリーズに関してはスチールに切り取られることへの抵抗はそんなにないですね。
ーご自身が行為をしている、そのことに意味があるというか、映像は一種のアーカイブでもありますよね。
宇多村:そうなんです。経験を通して感じたことが大きければ大きいほど、パフォーマンスをした直後に実際の映像はすぐには見れないことがあります。このシリーズの中で最も私の意図、想像を超えた作品「Red Line」は、環境に負荷が少なく、自然に戻っていく赤い顔料が白い崖の上に血のように叩きつけられる。なかなか命がけでやっているんですが、そこで映像として切り取る怖さを感じました。実際の経験があまりにも命がけなので、映像を見たときに「えっ。こんなになんでもないような感じで映っちゃうんだ。」という衝撃があって。自分にとっては最大の恐怖だったはずなのに、客観的な距離で見ると、コミカルにすら見えてしまう。

宇多村英恵「Red Line」2011 HD Video Performance
木下:コロナ禍で配信が増えたときに、音楽をやってる友人たちが言ってました。映像技術と音響とがどれだけ整っているかにもよるし、やっぱり生のライブとは比べられない。展覧会のカタログもそうかもしれませんが、その時の体感が薄れる場合はどうしてもある。逆に実際におこなったパフォーマンスを映像にしなかったことはあるんですか?
宇多村:それはとてもいい質問ですね。映像は無く、写真にのみ収めたという作品はあります。たしかに何も記録に残さないというのは、いいですね。ただ私の場合は、残された映像を通して、自分の行為の意味を問うプロセスがあり、客観的な鏡の役割があったので、大切でした。
本来のスタンスでいうと、経験に重きを置きたいタイプなんです。そこで経験することを大事にしていたい。映像におさめるにあたって、どのみち経験を閉じ込められないということを前提としたときに、じゃあ「映像作品」としてしまおうと。記録としてではなく。映像というのは経験を再現できるものではない。だったら最大限にその経験を収められる方法は何かを考えたときに、手持ちで撮影するとその場で動いている風の動きなどが捉えにくくなる。定点撮影にすることでその場所で起きている揺らぎだったり波だったりが見えやすいという意味で定点にしていました。
木下:私も落とし込めない体験というものが結構あると思っています。ずっと東京でアトリエを構えてその中で作品を作っていて、でも自分が動いた体験として何かを見るということもすごく大事にしています。大学の時、1ヶ月くらいアメリカとカナダを旅しました。ものすごい感動があり、学校に戻って何かに落とし込まければいけない気になって色々やってみるんですが、常に形にならない難しさがありました。時間が経って蓄積されて、ちがう形になって現れるということを私は繰り返してきているのだと思います。映像に撮って作品に、となったときに、その場で体験したものと大きく違ってくるという宇多村さんの感覚はすごく興味深いです。
宇多村:これもすごく皮肉なのですが、震災のときに私はフィンランドにいたので、私の震災の経験は、映像での経験だったんです。ニュースで流れてくる映像が全部上から撮られていて、さらに津波が地上の全てを流していく。それがある意味、人間と離れたような視座、神のような視点から見てしまったことへの違和感がありました。自分が当時作っていたシークレットパフォーマンスシリーズのことがフラッシュバックしたんです。あの作品は震災前に予震のように何かを感じて、私達の文明への問いとして行っていたことだったと振り返って思うのですが、それが現実に起きたようなショックがありました。それとやはり自分自身もそこにいれず、さらに家族の安否もわからない状況が何日も続いた経験が逆に、経験できなかったことに対して、本当はどういう衝撃だったのかというのをずっと追いかけているようなところがあります。逆にいなかったゆえに、そのまわりをぐるぐる問いながらこれまでやってきている。
木下:地震を関東で体験していても、実際被害の大きかった場所とは距離があって、俯瞰して映された景色はこれが今起こっていることなのかと思うくらい衝撃があったので映像のショックはすごく覚えています。
宇多村:人間の地上から離れた上空からの映像の視点は、もう少し膨らませて考えると、監視社会や、人間から離れた世界に存在するデジタルのアルゴリズム、私達が気づかない場所で情報を制御する支配的な存在を思い起こさせる視点でした。そのあとロンドンに帰ってからも募金活動をしたりしたのですが、私も茨城出身なので被災した友達も何人かいる状況の中で、やはり直接支援できないことに居ても立ってもいられなくなり帰国し、友人と被災地に支援物資を届けに行ったりしたこともありました。それは自分の視点を地上に取り戻すための行為だったのかなと、振り返って思いますね。
ーシークレットパフォーマンスシリーズを経て、震災のあとはどのように作品が変化していったんでしょうか。
宇多村:その頃から被写体になる自分の体がアジア人女性であるということの表象が、だんだん制限に感じるようになっていきました。自分のジェンダーをただ一人の人間であるというだけのシルエットにしたいと思い、カメラがだんだん遠ざかっていって、どんどん小さくなっていったんです。パフォーマンス映像は、「なぜ?」という自分の探求や問いを、見ながら考える場所だったんですが、そのような経緯から、自分ではなく、別の人をパフォーマーとして時空を起こすという方に移っていきました。でもそうすると今度は自分がホームベースとしていたリサーチとしての身体感覚が遠のいてしまったような気がしていました。現場に吹く風だったり、何かそこにある気配のようなものと対話していたところがあって、自分が去ったことでそれが遠のいてしまった。ただ、今回クラウトラウムで展示させてもらった海底の地層をガラスに閉じ込めた玉は、自分があのシリーズで感じていた風景との対話を、モノの制作過程で感じられた新しい経験でした。物質が熱変換を通して自ら動き出す様子を初めて見せられた作品で、それは自分の中では大きな発見でした。気候変動の関係もあり、移動することに対しても慎重になっているので、今回クラウトラウムで展示をした作品のように、何億年前の地上の風景など、想像上でしか辿り着けない風景を物質を通して表現できたのは、新しい地平線でした。

宇多村英恵「太古の空気-深海地層ガラス」2019 ガラス、陸源火山堆積の地底、鏡
木下:今回の展覧会に引き寄せて思い出すと、目の前のものを超えてくるという感じはすごくありました。作品から、その場の外側を想像するっていうことができる展覧会だと思ったんです。その外が続いている、そこだけに留まらないものというか。
ーSNSやニュースによって入ってくる情報にとらわれやすい中で、作品や展覧会も液晶画面を通して目撃したことであたかも完了したように錯覚してしまう怖さは日々感じています。そこに自覚はありつつも、正直なところ、そこに見えていないものを想像できる豊かさを自分の生活の中で保つのはなかなか難しかったりもする。このスペースが自宅を兼ねていたということもあり、ここでやってきた展覧会は、実際に自分が日常生活の中で生じた問いや違和感をいつも重ねていたと思います。一生活者としての問いかけを展覧会という形をとって人と共有したかったというか。この展覧会もコロナ禍という現実に直面したことによる実感がそのまま反映された、非常にシンプルなテーマだったと思います。
宇多村:今回の展覧会の「言葉でもなく、イメージでもなく」というタイトルに表現されている、大きな言葉で括られることで満足されてしまうようなことへの違和感、そこから見逃される何かをすくい上げたいというような姿勢に、すごく共感したんですよね。私の活動も、確かに気候変動とかそういう動機からやっていたかっていうと、それよりはどちらかというとこう、目の前の、もっとささやかなものから、人間は地球上にいてはいけない生物なのか?いや、そうじゃないはずだ、どういう生き方が人間としてあるということなんだろう、と問い直しながら、私達の近代という時代を見つめ直す作業だったんだと感じています。

右:宇多村英恵「萌芽シリーズ」2020 水彩 左:宇多村英恵「太古の空気-深海地層ガラス」2019 ガラス、陸源火山堆積の地底、鏡

会場風景

金川晋吾「portraits」2021 インクジェットプリント

会期最終日に展示された大木裕之のドローイング

金川晋吾「portraits」、会期最終日に展示された大木裕之のドローイングと写真