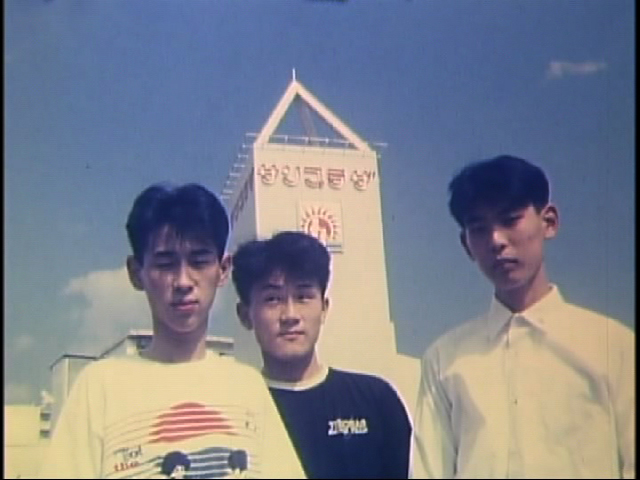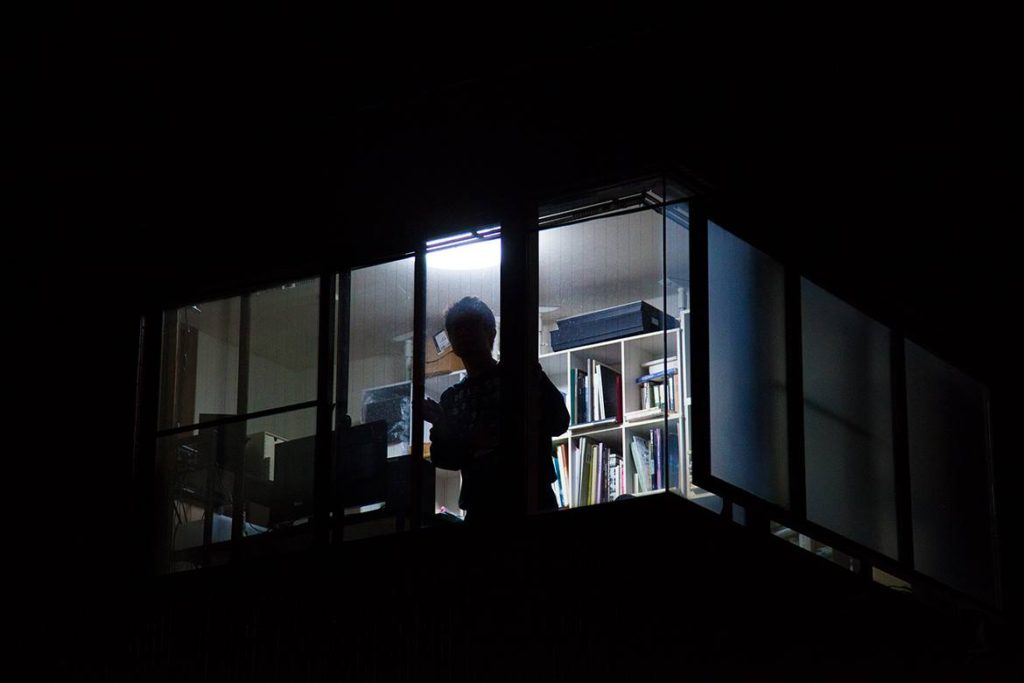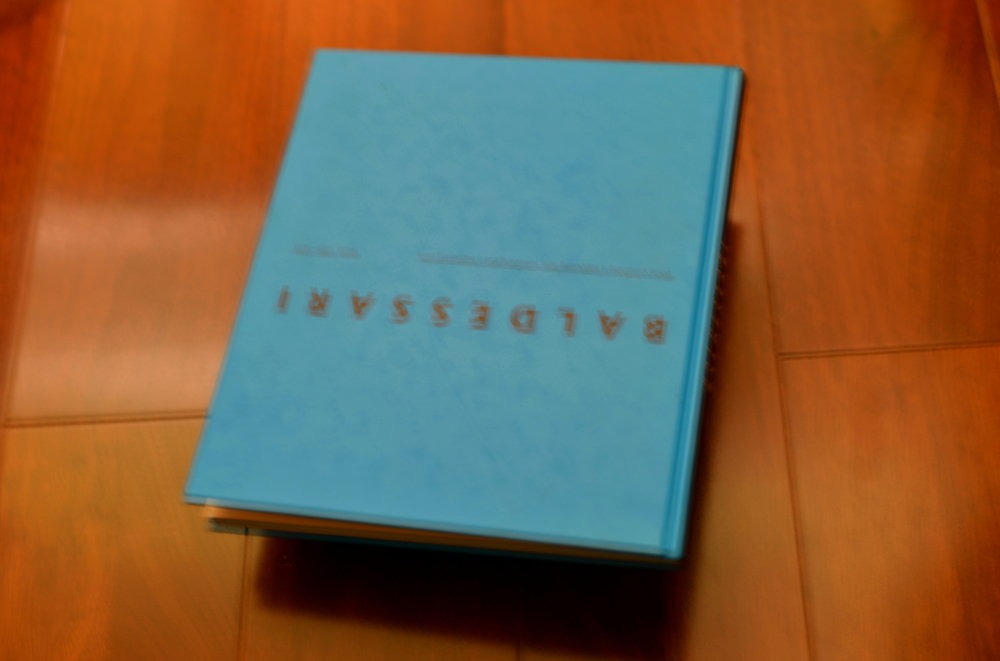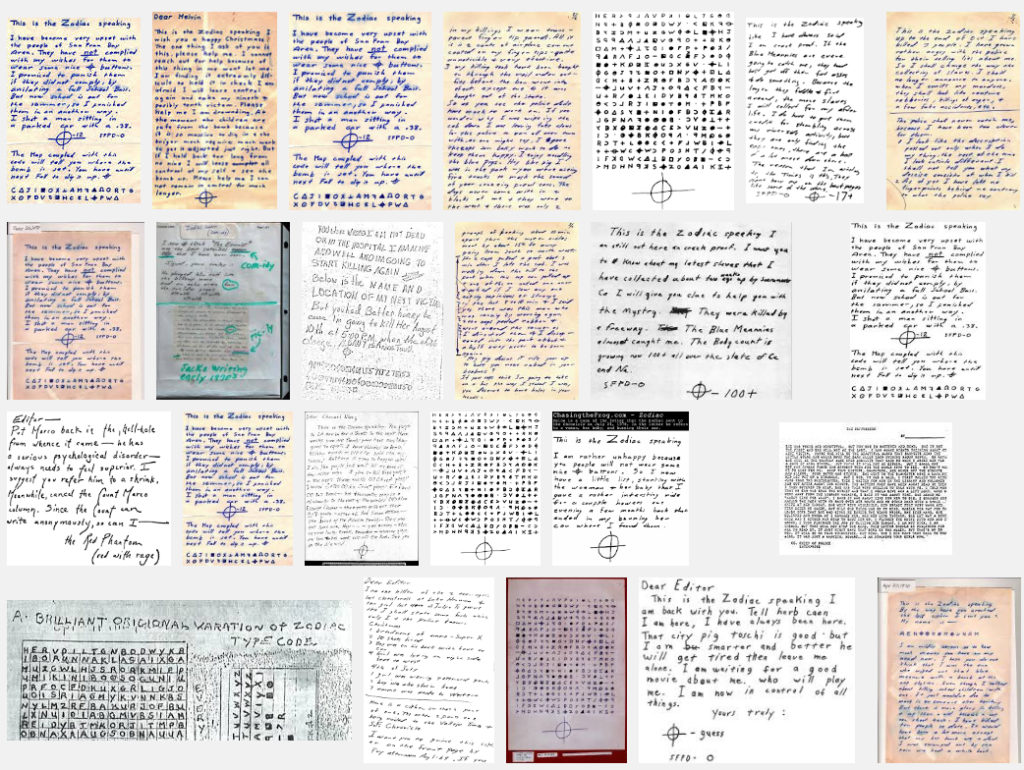event
宇多村英恵×木下令子 オンライン対談
2021年12月28日
展覧会「言葉でもなく、イメージでもなく、」が終わってちょうど一ヶ月が経ったところで、参加作家の木下令子さん、ニューヨーク在住の宇多村英恵さんによるオンライン対談をおこないました。自然の現象や事物の揺らぎに身を委ねながら形を成すお二人の作品制作は、一人の作家の人生やキャリアという枠組みの先にある、長い時間の移ろいを見据えているようにも感じられます。前半は改めて制作の原点を経由しながら、作品が後世に残っていくこと、美術作品に課せられるその永遠性について、木下さんを軸にお話を伺いました。後半は、発生から11年が経つ東日本大震災も振り返りながら、映像体験、身体的経験、その差異について宇多村さんを軸にお話を伺いました。
聞き手:下山彩(krautraum)
記録撮影:藤川琢史
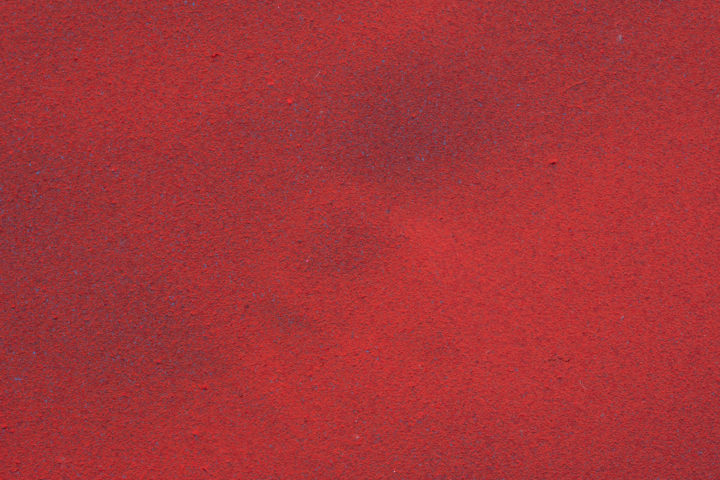
木下令子「日照時間」(部分)2021、アクリル絵の具、印画紙
-今回展示した木下さんの「日照時間」は印画紙を支持体としているため今後もゆっくり徐々に感光を続け、色が変化していく可能性を秘めています。十数年後やその先の将来に作品がどんな表情をしているかはまだ作者である木下さんご本人にもわからない。ご自身の作品が今後も後世に残っていくことや、作品が誰かの手に渡っていくこと、その移ろいをどのように捉えていますか。
木下:作家活動をしていく上では、作品は作者の手から離れたところで自立していきますし、もちろん人の手に渡ることも伴います。私は時間の経過そのものを絵に留めていくことはできないかという問いがあるので、変化という移ろい自体が作品であると言いたいです。そこに絵の形を借りているとも言えるかもしれません。
宇多村:自分の手を離れて寂しかったりすることはありますか?
木下:今はそういった感情を超えてくるようになりました。それでも、作品に対する偏愛のようなものは持っている方だと思います。宇多村さんのギンカクラゲ※1 もそうですが、もう出会えない自然が生んだものってありますよね。宇多村さんが「見つけた」というその瞬時の視点をとても感じました。何ものにも代えがたいし複製できるものではない。どう手放すか、そこは作家活動をしていく上で慎重に考えるところですね。

※1 宇多村英恵「未来の地層のスタディー」2019年、ギンカクラゲ 、マイクロプラスチック 採取場所:青森県 佐井村 仏ヶ浦
宇多村:時間も出会いですよね。木下さんの作品もその時の空気だったりいろんなものが出会ってできた作品で、二度と同じことは起きない。その時私たちがなんとなく感じている現在性が形に収められて、時間がたてば経つほど輪郭を持ってあの時こうだったんだ、というのがより鮮明にわかるような気がします。絵画という枠があるからそれをよく見れる形になってる。
木下:以前、中村麗さんがダヴィンチの「最後の晩餐」と私の作品を並べて書いてくださった文章 があります。※2 最後の晩餐は、作家が生きている間にすでに剥落が進んでいて、その後の環境 で状態は悪化したものの長年の修復が繰り返されて鮮やかに蘇った。でも作者は作品に 流れる歴史や時間をどこまで想像していただろう?という作品の運命を辿る内容を「時を刻む」と いう視点から、印画紙を使った私の作品と重ねて書いて下さっています。ー「画家の手を離れ てからの修復の時間も人為的であれ作品の一部であることになるのだろうか※2」。修復を否定し ているのではないけれど、ただ作者の意図とは全然違うものに変わってしまうという可能性もあるかもしれない。
宇多村:人の思いが時間を超えて乗っかって乗っかって。人の歴史ですよね。イエスキリストの聖書も何千年も経ると、人の気持ちだったり解釈だったり、願いみたいなもので変わってくるというか。それが歴史ということなのかなと思いました。委ねるということの先には人の気持ちがあり、作家の意図を超えて残したいという。
木下:作品自体が時を刻むなかで、誰がどう残していくのか。最近20代の絵描きが身近で亡くなって、残された作品を前にしました。実際に、サインも上下も詳細が不明のものが溢れていて本人の意思がどうしてもわからない。でも周りに残そうとする人がいると作品が整理されて人生が浮き立ってくるようでした。人の手を渡って残されていくことを目の当たりにして、また違った意味で作品の永遠とは何かを考えさせられました。

会場風景
宇多村:もともと私も絵がすごく好きで、昔は絵を描いていました。作品を外で展開したのは、2009年のロンドンのトラファルガースクエアというナショナルギャラリーの前の広場が最初です。ナショナルギャラリーって無料で伝統的な絵画や彫刻が公共の人たちに開かれている。そういう美術の殿堂的な場所の前で、お掃除のブラシと水で、アクションペインティングを描く、というアクションをしました。他の人にはその行為がお掃除にも見える、ということが私にとっては大きかったですね。西洋のパーマネントコレクションという、永久的な考え自体に違和感がどこかしらあったのかもしれません。キャンバスは地面で、ブラシで水を飛ばし、その地面の水を人が歩いて足跡がどんどん出てきたりする。そういう様々な痕跡が最後に蒸発して一つになり、絵になる。蒸発する儚いものを使って一時的に場を起こすというか。それが始まりだったんです。1回目、2回目は警察にすぐに止められてしまい、3回目で一通り行為を行うことができました。最後には「滑るから危ない」と言われて、止められましたけど。
木下:すごく共感するところがあります。制作をしていると「完成」という言葉がずっと付きまとってきますが、永遠をどう捉えるか、生活と制作の中で常にたくさんのことが発生し続けている感覚があって、完成という終わりを迎えようとする絵画制作にはずいぶん行き詰まって悩んできました。大学を出てアトリエを構えた時、改装する中で窓を大きく残したんですけど、ある時その窓から入る日差しが折り畳んでシワの寄った紙を日焼けさせていて。そこに別の作品制作で使用したスプレーガンの名残りの絵の具が付着して、今にも消え入りそうな繊細な状態で「絵」が勝手に出来上がっていたことがありました。すごく安価な紙でいずれ消えてしまうだろうと思いつつも、定着しきれていないようなその不安定さは、とても理想に近かったですね。最初は自分でもそれが果たして作品になるのか、作品と呼んでいいのか不安でした。でも呼ぼうと。しかしいざ作品として発表したときに、これが作品なんですか?どうやって保管するんですか?と聞かれることがすごく多かった。変化が目に見える事実を怖がるというか、永久性が前提なのだと。永遠とは、という問いは今も自分の制作の題材にもなっています。

木下令子「日照時間」2016、アクリル絵の具、印画紙
-今の技法に行きつく前には自分の筆跡を直接画面に残すことに抵抗があったとおっしゃっていましたよね。どんな表現をしていたんでしょうか。
木下:学生の頃は、主にインスタレーションであやとりなどを題材に作品を作っていました。あやとりというのは、その場ですぐ形ができるけど手を離せば解体されてしまう。空間に糸を使ってドローイングするアプローチでした。さっき宇多村さんが美術館の前で警察に注意されたという話がありましたけど、私も屋外に設置した作品が全部撤去されたことがありました。その時初めて絵画という枠組みの中では自由だったなと振り返ることができたり。大学を出たときにもう一度自分で自由に向かう画面があるんだというところを取り戻して、しっかり絵に戻ってきた感じがありました。当時、作品を記録するためにフィルムで写真を撮るようになリました。今の制作の間合いのようなものは、学生時代の暗室作業での経験が大きな影響を与えていると思います。直接画面に触れずに潜像を浮かび上がらせていく。フィルムの在り方や現像する過程が、筆をやめて塗装用のスプレーガンを用いた、画布に触れない間接的な手法に結びついたんです。
そこに至るまでには、実験的な制作が続きました。上京してきたばかりの頃、女性だとわかると大学には入れないと言われたことの衝撃から、自分の痕跡に対する抵抗感や葛藤が長くつきまとっていました。そういった呪縛のような言葉から逃れて、制作を自由に行いたいという想いのようなものがあったと思います。
それから2018年の個展のとき、与えられた現状、現象とともに絵を描くということを、自分では描かないという言葉を使ってステイトメントを書きました。その時、長く作品を見続けてくれていた批評家の友人から筆跡を残さずに神が描いたとされた聖画についての話を聞きました。個を出さずに自分なきものが描くという。サインの残されていない作者不在のような絵画や名を伏せた絵描きの存在は、ものすごく感銘を受けました。
宇多村:そういう姿勢というものが今の私たちの時代では少なくなっていま
木下:どうやって自分が絵を描き続けられるかという、気持ちの置きどころとしても少し救われるような話でした。今は強く強く自分を押し出すようなことが求められるけれど、それすら許されない現実もあったんだという。
自分の力だけで絵を描かない、自分なきものが描くという言葉は、描くことを放棄したと捉えられる事も多かったのですが、そこは自分が描き続けるために重要な部分で揺るがなかったですね。その辺にたまたま転がっていた都合の良さではなくて、自分の根底に在ったリアリティから自然とその態度で作り続けてきました。作品も数を経て、その意味が証明されて伝わるようになってきたのは、やっと最近のような気がしています。

木下令子「日照時間」2021、アクリル絵の具、印画紙
※2 「世界の医学・医療を知る MMJ」2017年4月号 中村麗「表紙のカルテ」より